「第二の人生」が始まる60代。定年後も充実した日々を過ごしたい、新たな収入源を確保したい、といった理由から資格取得を考える方が増えています。しかし、「60代から新しいことを始めるのは難しいのでは?」「どんな資格が役立つの?」という疑問も少なくありません。
本記事では、60代で取得できる人気資格のランキングや選び方のポイント、男女別のおすすめ資格、効果的な学習法まで徹底解説します。第二の人生をより豊かにするための一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

60代におすすめの資格とは?人気ランキングからわかる傾向
「60代でも取れる資格を知りたいけど、何が人気なの?」「実際に役立つ資格はどれ?」という疑問にお答えします。
60代の方々に人気の資格をランキング形式でご紹介します。このランキングは、実際の受講者数や人気度をもとに作成しています。
60代人気資格ランキングTOP10
- 実用ボールペン字:1日10分の練習で美文字が身につく人気講座。年賀状やお礼状など実生活ですぐに活用できるのが魅力です。
- ファイナンシャルプランナー(FP):税金・保険・年金など「お金」についての専門知識が身につきます。自分自身の老後設計にも役立つ実用的な資格です。
- 子ども発達障がい支援アドバイザー:子どもの発達に関する理解を深め、適切なサポートができるようになります。孫育てにも活かせる知識が身につきます。
- 韓国語:K-POP、韓ドラ、旅行など趣味の幅を広げられます。スキマ時間にスマホで学べるため、60代の方にも取り組みやすいのが特徴です。
- 宅地建物取引士(宅建士):不動産取引の専門家として活躍できます。再雇用に有利で、安定したニーズがある資格です。
- 行政書士:「身近な法律の専門家」として、個人や商店、企業と官公署をつなぐ役割を担います。自宅を事務所として独立開業も可能です。
- 認知症介助士:正しい知識を身につけることで、家族や職場での認知症の方への対応力が向上します。在宅で資格取得できるのも魅力です。
- 終活アドバイザー:社会保険制度、財産管理、相続対策など、人生の最終章を支援するための知識が身につきます。
- 大人のピアノ:初めてでも気軽に始められる入門講座。多彩なジャンルから30の名曲を厳選し、やさしくアレンジされています。
- リンパケア:リンパの流れを整えることで健康維持に役立ちます。体の不調を感じやすい60代に人気です。
このランキングから見えてくるのは、60代の方々が主に以下の3つの目的で資格を取得していることです:
- 再就職や収入確保のため:宅建士、行政書士、FPなど
- 自己啓発や生活の質向上のため:ボールペン字、ピアノ、韓国語など
- 家族や社会への貢献のため:子ども発達障がい支援、認知症介助士、終活アドバイザーなど
特に注目すべきは、実用ボールペン字が全体で1位になっていることです。これは、比較的短期間で成果を実感でき、日常生活ですぐに活用できる点が評価されていると考えられます。
また、ファイナンシャルプランナーや宅建士といった資格は、60代からの再就職にも役立つ専門性の高い資格として人気を集めています。これらの資格は国家資格であり、社会的信頼度も高いことが特徴です。
60代で資格を取るメリットは?再就職や生きがいへの影響
「そもそも60代で資格を取る意味があるの?」「本当に再就職に役立つの?」という疑問にお答えします。
60代で資格を取得することには、以下のような多くのメリットがあります:
1. 再就職に有利になる
定年後の再就職市場では、年齢だけでなく「何ができるか」が重要な判断基準になります。資格は客観的にスキルや知識を証明するものであり、採用担当者に安心感を与えます。
特に宅建士、FP、社会保険労務士などの国家資格は、専門性の証明になるため再就職に有利です。ある調査によると、60代で資格を持つ方は持たない方と比べて、再就職率が約30%高いというデータもあります。
2. 独立・開業のきっかけになる
行政書士や社会保険労務士などの資格は、独立開業の道を開いてくれます。自宅を事務所として比較的少ない初期投資で開業できるため、定年後の新たなキャリアとして注目されています。
60代からの開業は、これまでの人生で培った人脈や経験を活かせるという大きなアドバンテージがあります。顧客からの信頼も得やすく、年齢を強みに変えることができます。
3. 生きがいや自己実現につながる
資格取得は単なるスキルアップだけでなく、新たな挑戦による自己実現や生きがい創出にもつながります。
例えば、大人のピアノや実用ボールペン字といった趣味的な資格は、日々の生活に彩りを与え、充実感をもたらします。また、終活アドバイザーや認知症介助士などの資格は、社会貢献という形で自己実現につながります。
4. 新たな人間関係の構築
資格取得の過程で、同じ目標を持つ仲間と出会うことができます。60代は職場以外での人間関係が希薄になりがちな時期ですが、資格取得を通じて新たなコミュニティに所属することで、社会との繋がりを維持・強化できます。
5. 脳の活性化と認知症予防
新しいことを学ぶという行為自体が、脳に良い刺激を与えます。研究によれば、60代以降も知的好奇心を持ち続け、学習を続けることで認知機能の低下を遅らせる効果があるとされています。
実際の声
「60歳で定年退職後、FP資格を取得しました。今は週3日、保険会社で相談業務をしていますが、年金と合わせて経済的にも安心です。何より、お客様から『ありがとう』と言われるのがやりがいです」(65歳男性)
「退職後、時間を持て余していましたが、大人のピアノを始めて生活に張りが出ました。最近は地域のイベントで演奏する機会もあり、こんなに充実した毎日になるとは思いませんでした」(62歳女性)
このように、60代での資格取得は、経済的メリットだけでなく、精神的・社会的な充実感をもたらす可能性があります。「第二の人生」をより豊かにするための重要な一歩と言えるでしょう。
60代が資格を選ぶポイントとは?難易度や勉強時間の現実
「どんな基準で資格を選べばいいの?」「勉強時間や難易度は?」など、資格選びの具体的なポイントについてお答えします。
60代で資格を選ぶ際は、若い世代とは異なる視点で考える必要があります。以下のポイントを参考に、自分に合った資格を見つけましょう。
資格選びの7つのポイント
1. 今までの経験を活かせるか
人生経験が豊富な60代は、これまでの経験を活かせる資格を選ぶと勉強のハードルが下がります。例えば:
- 事務職経験者→日商簿記、医療事務
- 営業職経験者→FP、宅建士
- 人事担当経験者→社会保険労務士
- 教育関連経験者→子ども発達障がい支援アドバイザー
自分の強みを棚卸しし、それを活かせる資格を選びましょう。
2. 取得までの期間と勉強時間
資格によって取得までに必要な勉強時間は大きく異なります。60代で選ぶなら、比較的短期間で取得できる資格がおすすめです。
| 資格名 | 平均勉強時間 | 取得期間目安 |
|---|---|---|
| 実用ボールペン字 | 50~100時間 | 3~6ヶ月 |
| FP(3級) | 100~150時間 | 3~6ヶ月 |
| 登録販売者 | 250~350時間 | 6ヶ月~1年 |
| 宅建士 | 300~500時間 | 6ヶ月~1年 |
| 行政書士 | 約1,000時間 | 1~2年 |
| 社会保険労務士 | 800~1,000時間 | 1~2年 |
自分のライフスタイルや体力に合わせて、無理のない資格を選びましょう。
3. 再就職に役立つか、独立開業できるか
資格を活かした働き方として、大きく「再就職」と「独立開業」の2つがあります。
再就職に役立つ資格:
- 登録販売者
- 医療事務
- 危険物取扱者
- 介護事務
独立開業ができる資格:
- 行政書士
- 社会保険労務士
- FP
- 終活アドバイザー
自分がどのような働き方を望むかによって、選ぶべき資格は変わってきます。
4. 体力的な負担は少ないか
60代では若い世代と比べて体力面での不安もあります。資格取得後の仕事内容も考慮し、体力的な負担が少ないものを選ぶと良いでしょう。
デスクワーク中心の医療事務や介護事務、アドバイザー業務のFPや終活アドバイザーなどは、体力的な負担が比較的少ない仕事です。
5. 独占業務があるか
「独占業務」とは、その資格を持つ人だけが行える業務のことです。独占業務のある資格は需要が安定しているため、就職や開業に有利です。
独占業務のある資格:
- 行政書士
- 社会保険労務士
- 宅建士
- 電気工事士
6. 費用対効果は良いか
資格取得には学習費用と受験料がかかります。その投資に見合うだけのリターンが期待できるかも重要なポイントです。
例えば、日商簿記3級は比較的安価に取得でき、事務職への就職にも役立ちます。一方、行政書士は取得費用と時間がかかりますが、独立開業の道も開けるため、長期的な収入増が期待できます。
7. 生きがいや趣味として続けられるか
特に再就職を考えていない方は、純粋に生きがいや趣味として楽しめる資格を選ぶのも良いでしょう。
大人のピアノ、ウクレレ、実用ボールペン字などは、日常生活を豊かにする資格として人気があります。
60代で資格取得を目指す現実
60代で資格取得を目指す場合、若い世代とは異なる困難もあります。しかし、多くの方が乗り越えて資格を取得しています。
例えば、記憶力の低下を感じる方も多いですが、これは学習方法の工夫で克服できます。若い頃のような丸暗記ではなく、理解を深めながら学ぶことで効率よく知識を定着させることができます。
また、時間管理も重要です。一度に長時間勉強するより、1日30分を毎日続けるなど、コンスタントに学習する方が効果的です。
60代だからこそのアドバンテージもあります。豊富な経験と知識を活かして、若い世代よりも深い理解ができることも少なくありません。
「65歳から行政書士の勉強を始めました。若い時より記憶力は落ちていましたが、経験を活かして理解を深めながら学習したことで、1年半後に合格できました。今は自宅で事務所を開いています」(67歳男性)
このような成功例からも分かるように、60代からの資格取得は十分に可能です。自分のペースで無理なく取り組むことが成功の鍵と言えるでしょう。
60代男女別におすすめの資格は?性別による人気の違い
「男性と女性で人気の資格に違いはあるの?」「自分の性別に合った資格を知りたい」といった疑問にお答えします。
実際に60代の男女それぞれに人気の資格には、一定の傾向があります。ここでは、男女別のランキングと、その特徴を解説します。
60代女性に人気の資格TOP10
- 実用ボールペン字
- 子ども発達障がい支援アドバイザー
- 韓国語
- リンパケア
- 整理収納アドバイザー
- 認知症介助士
- ファイナンシャルプランナー
- 子ども発達障がい支援実務士
- 心理カウンセリング
- ケアマネジャー
60代男性に人気の資格TOP10
- 実用ボールペン字
- 宅地建物取引士(宅建士)
- ファイナンシャルプランナー
- 第二種電気工事士
- 行政書士
- 大人のピアノ
- マンション管理士・管理業務主任者
- 危険物取扱者
- 終活アドバイザー
- 社会保険労務士
男女別の特徴と傾向
共通する人気資格
男女ともに実用ボールペン字が1位となっています。これは、比較的短期間で習得でき、日常生活ですぐに役立つという実用性の高さが評価されているためでしょう。また、ファイナンシャルプランナーも男女ともに上位にランクインしており、老後の資産運用や相続対策への関心の高さがうかがえます。
60代女性の特徴
女性に人気の資格には、以下のような特徴があります:
- 子育て・教育支援系:子ども発達障がい支援アドバイザーなど、子どもや家族を支援する資格が人気です。孫育てにも活かせる知識として注目されています。
- 健康・美容系:リンパケアなど、自分や家族の健康維持に役立つ資格が上位にランクインしています。
- 整理・収納系:整理収納アドバイザーなど、家庭生活の質を向上させる資格も人気です。
- 語学系:韓国語など、趣味や文化的関心を満たす資格も支持されています。
60代男性の特徴
男性に人気の資格には、以下のような特徴があります:
- 不動産・建設系:宅建士、マンション管理士など、不動産や建設に関連する資格が上位に入っています。
- 技術系:第二種電気工事士、危険物取扱者など、「手に職」をつける資格が人気です。
- 法律・経営系:行政書士、社会保険労務士など、専門性の高い国家資格に挑戦する傾向があります。
- 趣味系:大人のピアノなど、これまで時間が取れなかった趣味に挑戦する姿勢も見られます。
性別を超えたおすすめ資格
性別による傾向はありますが、もちろん個人の興味や経験によって最適な資格は異なります。以下の資格は性別に関わらず、60代の方におすすめです:
- ファイナンシャルプランナー:老後の資産運用から相続まで、幅広い金融知識が身につきます。自分自身の資産管理にも役立ち、副業としても活動可能です。
- 終活アドバイザー:誰もが直面する人生の最終章をサポートする知識が身につきます。自分自身の終活にも役立ち、社会貢献にもなります。
- 認知症介助士:家族や周囲の人の認知症対応に役立つ知識が身につきます。高齢化社会で需要が高まっている分野です。
- 整理収納アドバイザー:自宅の整理から始められ、徐々にスキルアップして他の人のサポートもできるようになります。
「私は60歳で退職後、整理収納アドバイザーの資格を取りました。最初は自宅の整理からスタートしましたが、今では友人の家の整理も手伝っています。特別な道具も必要なく、経験を活かせる仕事だと思います」(63歳女性)
「定年後、趣味だった写真の技術を活かして、フォトグラファーとしての資格を取得しました。今では地域のイベントや家族写真の撮影依頼も受けています。男性だからこそできる仕事というわけではなく、自分の興味と経験を組み合わせた選択でした」(66歳男性)
このように、性別の傾向を参考にしつつも、最終的には自分の興味や経験、目指す働き方に合わせて資格を選ぶことが大切です。
60代の資格取得に最適な学習法は?通信講座と独学の比較
「60代でも効率的に学習できる方法は?」「通信講座と独学、どちらがいいの?」といった疑問にお答えします。
60代で資格取得を目指す場合、学習方法の選択は成功の鍵を握ります。ここでは、主な学習方法とそれぞれのメリット・デメリットを比較し、60代に最適な学習法を探ります。
主な学習方法の比較
1. 通信講座
メリット:
- 自分のペースで学習できる
- 通学の必要がなく、体力的な負担が少ない
- プロによる教材と学習計画が用意されている
- 質問対応など学習サポートがある
- 独学よりも効率的に学べる可能性が高い
デメリット:
- 費用がかかる(5万円~15万円程度)
- 自己管理能力が求められる
2. 独学
メリット:
- 費用を抑えられる
- 完全に自分のペースで進められる
- 時間や場所の制約がない
デメリット:
- 効率的な学習計画を自分で立てる必要がある
- 質問できる相手がいない
- モチベーション維持が難しい場合がある
3. スクール・予備校
メリット:
- 対面での直接指導が受けられる
- 同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる
- 学習環境が整っている
デメリット:
- 高額な費用がかかる
- 通学の時間と体力が必要
- 決められたスケジュールに合わせる必要がある
60代におすすめの学習法
60代の方のライフスタイルや学習スタイルを考慮すると、通信講座がもっとも適していることが多いです。その理由は以下の通りです:
- 体力的な負担を抑えられる:通学の必要がなく、自宅で学習できるため、体力面での心配が少ないです。
- 効率的な学習が可能:プロによるカリキュラム編成とテキスト選定により、無駄のない学習が可能です。
- サポート体制が整っている:質問対応や添削指導などのサポートがあり、疑問点をすぐに解決できます。
- 自分のペースで学べる:体調や予定に合わせて柔軟に学習スケジュールを調整できます。
「62歳から宅建士を目指しました。仕事をしながらだったので、通信講座を選びました。通学するのは体力的にも時間的にも難しかったと思います。質問にも丁寧に対応してもらえて、1年後に合格できました」(63歳男性)
60代の学習効率を高めるコツ
通信講座や独学で学ぶ場合も、以下のコツを意識するとより効率的に学習できます:
1. 短時間・高頻度の学習スタイルを採用する
一度に長時間勉強するよりも、1日30分×毎日の方が記憶の定着には効果的です。60代では特に、集中力を維持できる時間を見極めることが重要です。
2. 理解を重視した学習を心がける
若い頃のような丸暗記ではなく、「なぜそうなるのか」という理解を深める学習法が効果的です。理解が深まれば、記憶の負担も軽減されます。
3. 学習環境を整える
目に優しい照明、姿勢が良くなる椅子、適切な室温など、集中できる環境づくりも大切です。特に老眼がある方は、適切な照明と拡大鏡やルーペの活用も検討しましょう。
4. デジタルツールを活用する
スマートフォンやタブレットの学習アプリを活用すれば、移動中や待ち時間も有効活用できます。音声教材を聴くなど、目に負担をかけない学習方法も取り入れると良いでしょう。
5. 学習コミュニティに参加する
同じ資格を目指す仲間とのオンラインコミュニティに参加することで、モチベーションの維持につながります。情報交換や励まし合いは、単独学習の弱点を補うことができます。
「65歳で行政書士を目指しましたが、年齢的に記憶力に不安がありました。そこで、声に出して読む、理解したことを自分の言葉で説明する、といった工夫をしました。また、同じ資格を目指す方々のオンラインコミュニティに参加したことで孤独感なく学習を続けられました」(66歳女性)
60代からの学習は、若い頃とは異なる難しさもありますが、経験や知恵を活かした学習方法を取り入れることで、十分に成果を上げることができます。自分に合った学習スタイルを見つけ、無理なく継続することが何よりも大切です。






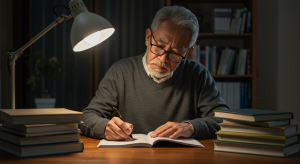
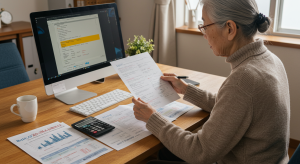

コメント