定年という大きな節目を迎え、これからの人生をどう過ごそうか考えている方も多いのではないでしょうか。まだまだ働き続けたい、あるいは新しい分野で自分の可能性を試してみたい。そんな意欲的なシニア世代にとって、資格取得は新たなキャリアを切り拓くための強力な武器となります。しかし、学び直しには費用がかかるもの。そこで注目したいのが、国が提供する「教育訓練給付金」制度です。この制度を賢く活用すれば、費用負担を大幅に軽減しながら、専門的なスキルを身につけることが可能です。この記事では、定年後のキャリアに本当に役立つ資格は何か、そしてハローワークを通じて利用できる教育訓練給付金制度の詳細と、その申請方法から注意点まで、あなたのセカンドキャリアを成功に導くための情報を網羅的に解説していきます。
教育訓練給付金制度とは
教育訓練給付金は、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とした制度です。厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、その経費の一部が支給されます。多くの方が定年退職と共に縁遠い制度だと思いがちですが、60歳を過ぎていても雇用保険に加入しており、かつ加入期間などの要件を満たしていれば、この制度を十分に活用することができます。実際に、定年後も継続して働いている方や再雇用中の方が、現在の仕事の維持や新たな資格取得を目指して利用するケースは少なくありません。この給付金制度には大きく分けて3つのタイプが存在し、それぞれ支給される金額や対象となる教育訓練の内容が異なっています。
教育訓練給付金の受給資格
教育訓練給付金を受給するためには、雇用保険の加入期間に関する条件をクリアする必要があります。給付金の種類によって求められる加入期間が異なるため、ご自身がどの条件に合致するのかを事前にしっかりと確認することが重要です。
一般教育訓練給付金の受給資格は、雇用保険に加入していた期間が通算で3年以上必要です。ただし、初めてこの給付金制度を利用する方に限り、加入期間が1年以上あれば受給資格が認められます。この条件は比較的緩やかであるため、定年後に再雇用された方など、雇用保険への加入期間が短い場合でも活用しやすいのが特徴です。
特定一般教育訓練給付金の受給資格も、基本的には一般教育訓練給付金と同様です。雇用保険の加入期間が3年以上、初めて利用する場合は1年以上あれば受給できます。この給付金は、特に速やかな再就職を目指す方に適した訓練が対象となっています。
専門実践教育訓練給付金の受給資格は、他の二つよりも少し厳しく設定されています。雇用保険の加入期間が3年以上必要であり、初めて利用する場合でも2年以上の加入期間が求められます。加入期間の条件は長くなりますが、その分、支給される金額が大きく、長期的な視点でのキャリア形成を目指す方にとっては非常に魅力的な制度と言えるでしょう。
また、一度離職された方がこの制度を利用する場合には注意が必要です。雇用保険の資格を喪失した日、つまり離職日の翌日から受講開始日までの期間が1年以内でなければなりません。定年退職後に資格取得を考えている方は、退職してから1年以内に講座を開始する必要があるため、計画的な準備が不可欠です。さらに、受講を開始する日の前日から遡って3年以内に、いずれかの教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、新たに給付金を受け取ることはできません。過去に受給経験がある方は、前回の受給から3年以上が経過しているかを確認しましょう。
一般教育訓練給付金
一般教育訓練給付金は、3種類ある給付金の中で最も幅広い講座を対象としている、いわば入門的な制度です。受講にかかった費用の20%、上限として10万円が訓練を無事に修了した後に支給されます。対象となる資格講座は多岐にわたり、例えば簿記検定や宅地建物取引士、医療事務、介護事務など、多様な分野の資格が含まれています。これらの多くは比較的短期間で取得が可能であり、定年後に全く新しい分野へ挑戦してみたい方や、ご自身の趣味を活かした仕事に就きたいと考えている方に最適な選択肢と言えるでしょう。
特定一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練給付金は、より速やかな再就職や早期のキャリア形成に直結する、専門性の高い教育訓練を対象としています。2024年10月以降に開講される講座の場合、教育訓練にかかった経費の40%、上限20万円が訓練修了後に支給されます。さらに、この訓練を通じて資格を取得し、修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合には、支給率が50%、上限25万円まで引き上げられます。対象となる資格には、税理士や社会保険労務士、行政書士といった専門的な士業資格や、大型自動車免許、介護職員初任者研修などが含まれています。定年後もこれまでの経験や専門性を活かしてしっかりと働きたい方、あるいは新しい分野で確実に就職を果たしたいという強い意志を持つ方にとって、非常に心強い制度です。
専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練給付金は、3つの給付金制度の中で最も手厚い支援を受けられるものです。この制度は、看護師や介護福祉士、保育士、建築士など、業務独占資格や名称独占資格といった、取得することで特定の専門職に就くことが可能となる、高度な資格の取得を目指す長期的な課程を主な対象としています。
2024年10月以降に開講する講座を例に挙げると、教育訓練経費の50%、年間で最大40万円が、訓練を受けている期間中6か月ごとに分割して支給されます。さらに、訓練を修了し資格を取得した上で、1年以内に雇用保険の被保険者として就職が決まった場合には、支給率が70%、年間上限56万円まで大幅に増額されます。加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合には、最終的に教育訓練経費の80%、年間上限64万円という非常に手厚い支援を受けることが可能です。
ただし、この手厚い給付金を受けるためには、いくつかの事前の手続きが必要となります。まず、ハローワークの訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ご自身のキャリアプランを明確にするためのジョブ・カードの交付を受けなければなりません。その上で、受講開始日の2週間前までに、改めてハローワークで受給資格の確認手続きを完了させる必要があります。
定年後に役立つ資格
定年後のキャリア形成に役立つ資格は、目指す業界や職種によって実にさまざまです。ここでは特に、60歳を過ぎてからでも活躍の場が広く、需要が高い分野の資格を具体的に紹介します。
介護分野の資格
介護分野は、シニア世代がその人生経験を活かし、最も活躍しやすい分野の一つと言えるでしょう。統計によれば、60歳以上の介護職員が占める割合は16.6%にものぼり、特に訪問介護員にいたっては平均年齢が50.5歳、実に4人に1人が60歳以上というデータもあります。さらに、60歳以上の介護職員のうち約1割は、直近1年以内に入職しており、これは60歳を過ぎてから新たに介護の仕事に就く方が決して少なくないことを示しています。
介護職員初任者研修は、介護の資格がない状態からでも目指せる最も基本的な資格です。この研修を修了することで、食事や入浴の介助といった身体介助の仕事に従事できるようになります。研修期間は約1か月から3か月程度と比較的短く、介護の基本的な知識と技術を体系的に学ぶことができます。修了後は、介護施設や訪問介護事業所など、非常に幅広い職場で働く道が開かれます。
介護福祉士実務者研修は、介護職員初任者研修の一つ上のレベルに位置づけられる資格であり、介護福祉士国家試験の受験資格を得るために必須となります。より専門的な知識と技術を習得することで、キャリアアップに直結し、年齢や性別に関わらず長く安定して働ける専門職としての道が拓けます。
介護事務は、介護施設での受付や各種手続き、介護報酬の請求業務(レセプト作成)など、事務全般を担当する仕事です。複数の認定団体が資格を設けており、比較的取得しやすいのが特徴です。体力的な負担が少ないデスクワークが中心となるため、体力に自信がない方でも安心して始められるキャリアとして、定年後の選択肢として高い人気を誇ります。
福祉住環境コーディネーターは、学歴や年齢、実務経験といった受験資格の制限が一切ないため、誰でも挑戦できる資格です。高齢者や障がいを持つ方が、自宅で安全かつ快適に暮らせるよう、住宅改修などの住環境を提案する専門家です。介護職の資格と組み合わせることで、利用者に対してより多角的で質の高いサービスを提供できるようになります。
医療分野の資格
医療事務は、総合病院や大学病院といった大規模な医療機関だけでなく、地域に根差したクリニックなどでも安定した需要があり、60歳以上を対象としたパートタイムの求人も比較的多く見られます。主な仕事内容は、受付業務、診療報酬請求業務(レセプト作成)、カルテの管理など多岐にわたります。医療機関は全国どこにでもあるため、将来的に引っ越しや転居があった場合でも、仕事を見つけやすいという大きなメリットがあります。医療事務関連の資格には、医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)や医療事務管理士技能認定試験、そして最難関とされる診療報酬請求事務能力認定試験など、複数の種類が存在します。
専門的な資格
税理士、社会保険労務士、行政書士といった、いわゆる「士業」と呼ばれる専門資格は、一度取得すれば定年後も長く働き続けることが可能な、非常に強力な資格です。これらの資格は取得までの難易度が高いという側面はあるものの、独立開業という選択肢も現実的になり、自分の裁量とペースで仕事を進めることができます。これまでの現役時代に培った経験や人脈を直接活かせる分野でもあり、教育訓練給付金の対象講座も多いため、費用を抑えながら挑戦することが可能です。
宅地建物取引士(宅建士)は、不動産の売買や賃貸の仲介といった取引において不可欠な国家資格です。不動産業界では、一定規模以上の事業所に宅建士を設置することが法律で義務付けられているため、常に安定した需要があります。定年後に不動産会社でパートタイムとして勤務するなど、比較的柔軟な働き方ができるのも魅力です。宅建士の資格取得講座も教育訓練給付金の対象となっており、費用負担を軽減しながら合格を目指せます。
さらに、宅建士とファイナンシャルプランナー(FP)のダブルライセンスを取得することは、定年後のキャリアをより強固なものにします。ファイナンシャルプランナーの試験科目には不動産分野が含まれているため、宅建士の学習経験を活かして効率的に学習を進めることができます。この二つの資格を併せ持つことで、不動産と資金計画の両面からワンストップで顧客にアドバイスできる専門家として、自身の市場価値を大きく高めることができるでしょう。
危険物取扱者は、特に定年後の60代男性に人気のある資格です。ガソリンスタンドや化学工場、石油関連施設など、危険物を貯蔵・取り扱いする施設では、この資格を持つ人材が法律で義務付けられており、有資格者は常に重宝されます。特に乙種第4類(引火性液体)は、私たちの生活に身近なガソリンや灯油などを扱えるため需要が高く、実務経験がなくても受験できることから、挑戦しやすい資格として知られています。
IT分野の資格
現代社会において、ITスキルはあらゆる職場で求められる基本的な能力となっています。デジタル化の波は今後ますます加速していくため、ITに関する資格を取得しておくことは、就職先の選択肢を大きく広げることに繋がります。特に、MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)は、WordやExcelといったビジネスソフトの操作スキルを客観的に証明する資格であり、事務職を希望する方にとっては非常に有利に働くでしょう。
その他の実用的な資格
簿記検定は、企業の経理や会計に関する基礎知識を証明する、言わずと知れた定番の資格です。特に日商簿記の3級や2級を取得しておけば、中小企業の経理事務などでその知識を十分に活かすことができます。定年後にパートタイムで経理の仕事に就きたいと考えている方には、特におすすめです。
ファイナンシャルプランナー(FP)は、金融商品、保険、税金、年金、不動産など、個人のお金に関する幅広い知識を持つ専門家です。この資格の学習を通じて、定年後のご自身の生活設計に不可欠な知識を体系的に深めることができるだけでなく、他者へのアドバイスという形で仕事に繋げることも可能です。自分自身のライフプランニングに直接役立つという点でも、非常に実用的な資格と言えるでしょう。
教育訓練給付金の申請方法
教育訓練給付金の支給申請手続きは、お住まいの地域を管轄するハローワークの窓口で行います。申請に必要な書類や手続きの具体的な流れは、利用する給付金の種類によって異なりますので、注意が必要です。
一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の場合、指定された講座をすべて受講し、修了した後に申請手続きを行います。講座の実施機関から発行される修了証明書、領収書、そしてご自身の雇用保険被保険者証など、必要書類を持参してハローワークの窓口に提出します。この申請には期限があり、受講修了日の翌日から起算して1か月以内に手続きを完了させなければなりません。
一方、専門実践教育訓練給付金の場合は、手続きがより段階的になります。まず、講座の受講を開始する前に、ハローワークの訓練対応キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受ける必要があります。この面談を通じて、ご自身のキャリアプランをまとめたジョブ・カードの交付を受けます。その後、受講開始日の2週間前までに、このジョブ・カードなどを持参して、ハローワークで受給資格の確認手続きを済ませる必要があります。受講が開始された後は、原則として6か月ごとに支給申請を行います。そして、すべての課程を修了した後、最終的な支給申請を行い、その後の資格取得や就職の状況に応じて、追加の給付金を受け取ることができます。
対象講座の検索方法
現在、教育訓練給付金の対象として厚生労働大臣の指定を受けている講座は、インターネット上の「教育訓練講座検索システム」で簡単に検索することができます。厚生労働省のウェブサイトからこのシステムにアクセスし、取得したい資格名や学びたい分野、お住まいの地域などの条件を入力して検索することで、対象となる講座の一覧が表示されます。
この検索システムでは、講座の名称や実施している教育機関、受講にかかる期間や費用、そして対象となる給付金の種類といった詳細な情報を確認することが可能です。もし気になる講座が見つかった場合は、直接その実施機関に問い合わせて、カリキュラムの具体的な内容や受講の条件などを詳しく確認することをおすすめします。また、お近くのハローワークの窓口でも、教育訓練給付金の対象講座について相談することができます。専門のキャリアコンサルタントが、あなたの希望やキャリアプランに沿った最適な講座を提案してくれるでしょう。
定年後の資格取得成功事例
実際に定年後に資格を取得し、新たなキャリアで活躍している方の事例は、これから挑戦しようと考えている方にとって、大きな勇気と具体的なヒントを与えてくれます。
東京都在住のある65歳の女性は、定年退職後に介護職員初任者研修を修了し、現在、訪問介護員として生き生きと働いています。彼女は元々、障害福祉分野の社会福祉法人で事務職として定年まで勤め上げた経験の持ち主でした。資格取得のきっかけは、ある本を読んだことだったと言います。訪問介護という仕事が、介護される側だけでなく、その家族にとってもいかに重要で尊いものであるかを知り、「自分もその一端を担ってみたい」という気持ちが芽生えたそうです。この事例は、定年後という節目に、全く新しい分野へ挑戦する勇気が、いかに充実したセカンドキャリアに繋がるかを示しています。
彼女の学習プロセスは、約半年間にわたり、毎週土曜日に電車で学校に通い、一日中講習を受けるというものでした。最初のうちは物珍しさも手伝って非常に楽しかったそうですが、終盤に近づくにつれて疲れも溜まり、早く資格を取って終わりたいと感じることもあったと正直に語っています。しかし、講習や課題で学ぶ内容は、自分自身の老後にも直接関わることであり、結果として非常に勉強になったと振り返っています。
現在の仕事のやりがいについて尋ねると、在宅での生活を続けながら一人で懸命に生きる高齢者の方々との出会いは、何物にも代えがたい貴重な経験だと感じているそうです。もちろん、人間関係ですから様々な方がいますが、相性の良い利用者さんと出会えた時の喜びは格別だと語ります。
この女性は、これから資格取得を考える同世代の方々へ、「介護という分野に強い嫌悪感がないのであれば、ぜひ取っておいた方が良い資格です」とアドバイスしています。自分や家族の将来のためにも大変勉強になる上、シニア世代にとっては求職活動の大きな助けになるとのこと。そして、定年後に資格を活かした仕事を見つけるための重要なコツとして、「過去の栄光は一旦忘れ、新しい気持ちで求職活動に臨むこと」を挙げています。
定年後の資格取得を成功させるポイント
定年後に資格取得を目指す際には、いくつかの重要なポイントを押さえることで、学習効果を最大限に高め、成功の確率を上げることができます。
まず最も大切なのは、ご自身の興味や適性、そしてこれまでのキャリアをじっくりと振り返り、どの分野で新たに活躍したいのかを明確にすることです。単に「取得しやすいから」という理由だけで資格を選んでしまうと、学習のモチベーションを維持するのが難しくなります。前述の成功事例の女性のように、ご自身が心から興味を持てる分野を選ぶことが、学習を継続するための最大の原動力となります。
次に、資格を取得した後の具体的な働き方をイメージすることも不可欠です。フルタイムで再び組織の一員として働きたいのか、それとも時間を柔軟に使えるパートタイムが良いのか、あるいは独立開業を目指すのか。ご自身の理想のライフスタイルに合った働き方をあらかじめ考えておくことで、取得すべき資格もより明確になります。
具体的な学習計画を立てることも極めて重要です。定年後は比較的時間に余裕が生まれる一方で、長年のブランクから学習習慣そのものが途切れてしまっているケースも少なくありません。決して無理のないペースで、しかし継続的に学習できる計画を立てましょう。最近では、通信講座やオンライン講座も非常に充実しており、ご自身のペースで効率的に学習を進めることが可能です。
そして、同じ目標を持つ仲間を見つけることも、モチベーションを維持する上で非常に効果的です。資格取得のための学校やセミナーに参加すれば、情報交換をしたり、時には励まし合ったりできる仲間と出会えるでしょう。特に同世代の受講生と知り合うことは、定年後の生活や仕事に関する悩みを共有できるという点でも、大きなメリットとなります。
最後に、教育訓練給付金制度を最大限に活用するためには、早めの情報収集と計画的な準備が不可欠です。特に専門実践教育訓練給付金のように、受講を開始するかなり前から申請手続きが必要となる給付金もあるため、常に余裕を持ったスケジュールを組むことを心がけましょう。
教育訓練給付金活用のメリットとデメリット
教育訓練給付金制度は非常に魅力的な制度ですが、活用するにあたっては、そのメリットとデメリットの両方を正しく理解しておくことが重要です。
教育訓練給付金のメリット
この制度の最大のメリットは、何と言っても受講費用の経済的負担を大幅に軽減できる点にあります。一般教育訓練では受講費用の20%、特定一般教育訓練では最大で50%、そして専門実践教育訓練に至っては最大で80%もの給付を受けることが可能です。特に専門実践教育訓練の場合、年間の上限額は64万円、これを最大3年間受給できるとすると、合計で192万円もの巨額な支援を受けられる可能性があるのです。
また、働きながらでも受講しやすいという点も大きなメリットです。多くの対象講座が夜間や土日、あるいはオンライン形式で提供されているため、現在の仕事を続けながらでも無理なくスキルアップを目指すことができます。これは、定年後に再雇用などで働いている方にとっても、非常にありがたいポイントです。さらに、国が指定した講座であるため、その教育内容には一定の質が保証されており、安心して受講できるという信頼感もあります。
教育訓練給付金のデメリット
一方で、いくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。
最も大きなデメリットは、講座を途中で辞めてしまった場合には、給付金を一切受け取ることができないという点です。給付金の支給は、あくまで講座を修了したことを証明する「修了証明書」の提出が前提となります。万が一、健康上の理由や家庭の事情などで受講を続けられなくなったとしても、それまでに支払った費用に対する給付は行われないため、受講を開始する前には慎重な計画と覚悟が必要です。
また、受講費用は原則として一旦全額を自己負担で支払う必要があることも忘れてはなりません。給付金が支給されるのは、講座が修了した後、あるいは受講中の定められた時期であるため、一時的にまとまった資金を準備する必要があります。受講料が数十万円にのぼる講座も少なくないため、事前に資金計画をしっかりと立てておくことが重要です。
申請手続きがやや複雑で、ハローワークに何度も足を運ぶ必要があることも、人によってはデメリットと感じるかもしれません。特に専門実践教育訓練給付金を利用する場合には、受講前のキャリアコンサルティングやジョブカードの作成など、複数のステップを踏む必要があります。各種手続きには期限が設けられているため、スケジュール管理が非常に重要になります。
定年後のキャリア形成における注意点
定年後に資格を取得し、新たなキャリアを築いていこうとする際には、いくつか心に留めておくべき注意点があります。
まず、資格取得そのものが目的になってしまわないように意識することが大切です。資格はあくまで、希望する仕事に就くための手段であり、ゴールではありません。資格を取得しても、実務経験がないことを理由に、採用が見送られるケースも残念ながら存在します。可能であれば、ボランティア活動や短期のアルバイトなどを通じて、少しでも実務経験を積んでおくことを検討しましょう。
年齢を理由に採用を断られてしまうこともあるかもしれませんが、そこで諦めずに粘り強く応募を続けることが何よりも重要です。近年では、60歳以上の人材を積極的に採用している企業や、シニア世代が持つ豊かな経験を高く評価してくれる職場も確実に増えています。特に介護分野などでは、シニア世代の採用に非常に積極的な事業所が多く見られます。
ご自身の体力や健康状態に合わせて、無理のない働き方を選ぶことも、長くキャリアを続けるためには不可欠です。フルタイムでの勤務が体力的に難しいと感じる場合は、パートタイムや在宅ワーク、週に数日だけの勤務など、柔軟な働き方を探しましょう。自分の体調や生活リズムを最優先に考えることが、結果的に充実したセカンドキャリアに繋がります。
そして、現役時代のように給与や待遇といった条件面にこだわりすぎず、仕事そのもののやりがいや、社会との繋がりを重視することも、定年後のキャリアを豊かにする上での大切なコツです。収入のためだけでなく、生きがいや社会貢献といった新たな価値観で仕事を選ぶことで、これまでとは違った発見や満足感を得られるはずです。
定年後の再就職と支援制度
資格を取得した後は、いよいよ実際に仕事を見つける段階へと進みます。幸いなことに、現代の日本では、定年後の再就職をサポートするための様々な支援制度やサービスが充実しています。
統計データを見ると、60代前半の男性の8割以上、女性の6割以上が何らかの収入を伴う仕事に就いています。さらに60代後半に目を向けても、男性の6割以上、女性の4割以上が就労しており、多くのシニア世代が定年後もアクティブに働き続けていることがわかります。この事実は、定年後の再就職が決して特別なことではなく、ごく一般的な選択肢となっていることを力強く示しています。
活用できる支援制度やサービスは多岐にわたります。まず、ハローワークは、国が運営する機関として、無料で膨大な数の求人情報を提供しています。基本的な求人情報の検索や雇用保険関連の手続きには最適ですが、より個別の手厚いサポートを望む場合は、他のサービスとの併用が効果的です。
産業雇用安定センターは、キャリア人材バンクとして、再就職を目指すシニアと企業とのマッチングを専門的に支援しています。また、近年ではシニア専門の人材紹介会社や派遣サービスも非常に増えています。これらのサービスでは、専任のアドバイザーが応募書類の添削から面接対策、さらには企業との条件交渉まで、一貫して無料でサポートしてくれます。「定年なし」の求人や、シニアの経験を高く評価する企業の求人を多数保有しているのが大きな強みです。
再就職の準備においては、これまでのキャリアで培った経験とスキルが最大の武器となります。具体的な実績や成果を職務経歴書に詳細に記載し、ご自身の価値を明確にアピールしましょう。そして、取得した資格は、即戦力であることを証明する何よりの証です。履歴書や職務経歴書には、資格名を正確に記載し、新しい分野に挑戦する意欲も伝えましょう。面接の場では、年齢を重ねたからこその柔軟性や謙虚な姿勢を示すことも、採用を勝ち取るための重要なポイントとなります。
まとめ
定年後のキャリア形成において、資格取得が非常に有効な手段であることは間違いありません。そして、その挑戦を力強く後押ししてくれるのが、ハローワークの教育訓練給付金制度です。この制度を賢く利用することで、経済的な心配をすることなく、新しいスキル習得に集中できます。
介護、医療、専門的な士業、IT関連など、60歳を過ぎてからでも十分に活躍できる資格は数多く存在します。大切なのは、ご自身の興味や適性、そして理想のライフスタイルに合った資格を見極め、計画的に学習を進めていくことです。
教育訓練給付金には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。まずは「教育訓練講座検索システム」などを活用して、ご自身が目指す資格がどの給付金の対象となるのかを調べてみることから始めましょう。
資格は、取得してからが本当のスタートです。ハローワークやシニア専門の人材紹介サービスといった多様な支援をフルに活用し、自信を持って再就職活動に臨んでください。多くの同世代がすでにセカンドキャリアで輝いているという事実が、あなたの背中を押してくれるはずです。年齢という枠にとらわれることなく、ご自身の無限の可能性を信じて、未来への新たな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。





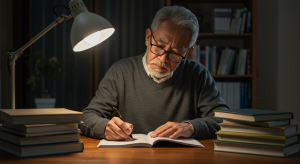
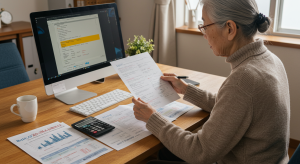


コメント