人生100年時代を迎えた現代において、60代からの新たなキャリアチャレンジが注目されています。その中でも、ケアマネジャー(介護支援専門員)への挑戦は、これまでの豊富な人生経験を活かしながら社会貢献できる魅力的な選択肢として多くの方に選ばれています。高齢化社会が進む日本では、ケアマネジャーの需要は年々高まっており、特に60代の方々が持つ同世代への理解力や人生経験は、利用者やその家族にとって心強い存在となります。しかし、60代からケアマネジャーを目指す場合、受験資格や実務経験の要件について正確に理解することが成功への第一歩となります。本記事では、60代の方がケアマネジャーになるために必要な受験資格と実務経験について、最新の制度情報とともに詳しく解説いたします。
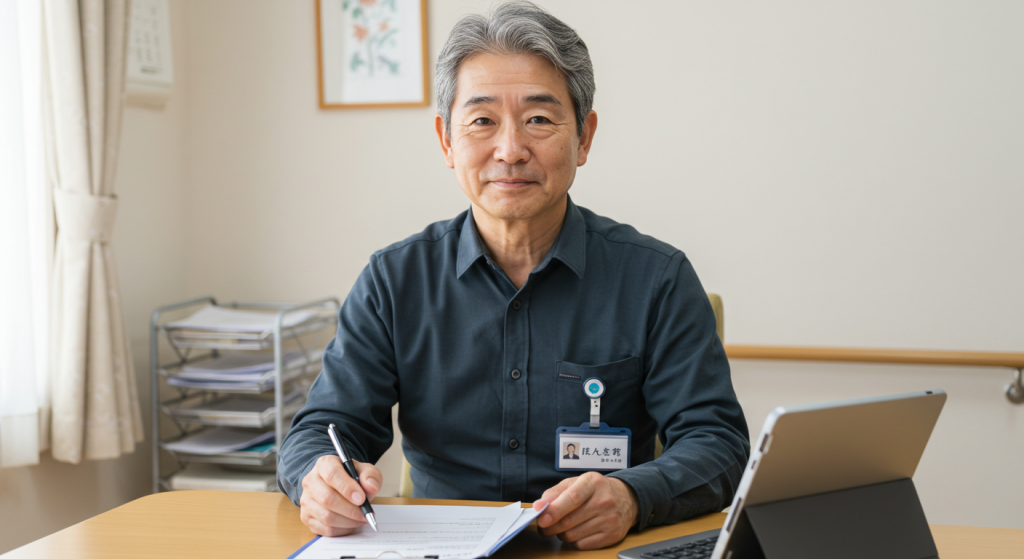
ケアマネジャー試験の基本的な受験資格要件を理解する
ケアマネジャー試験の受験資格は、厚生労働省が定める明確な基準があります。2025年現在の受験資格は、介護福祉士などの特定の国家資格等に基づく業務または相談援助業務の実務経験が5年以上(かつ従事日数900日以上)が必要とされています。この基準は年齢に関係なく適用されるため、60代の方でも同じ条件を満たす必要があります。
実務経験期間については、試験日前日までに満たしていることが求められており、常勤である必要はありません。これは60代の方にとって非常に重要なポイントです。非常勤やパートタイムなど、1日の勤務時間が短くても1日勤務したものとして計算されるため、定年退職後にパートタイムや非常勤として介護分野で働きながら実務経験を積むことが可能です。
この柔軟な勤務形態の認定は、60代からケアマネジャーを目指す方にとって大きなメリットとなります。体力的な制約を考慮しながら、無理のない範囲で実務経験を積み重ねることができるからです。また、複数の事業所での経験を合算することも可能なため、様々な介護現場での経験を通じて幅広い知識とスキルを身につけることができます。
60代での受験に年齢制限はない事実
多くの方が気になる年齢制限についてですが、ケアマネジャー試験には年齢制限が一切設けられていません。実際に、50代から60代の方々が活躍している求人情報も多数あり、現場では60代のケアマネジャーが重要な役割を担っています。むしろ、60代の方々が持つ豊富な人生経験や職業経験は、利用者やその家族との関係構築において大きなアドバンテージとなることが多いのです。
介護を必要とする高齢者の多くは60代以上の方々です。同世代または年上の方からの助言やサポートは、利用者にとって理解しやすく、信頼感を得やすい傾向があります。また、家族介護の経験がある60代の方であれば、介護者家族の心情をより深く理解することができ、適切なアドバイスや支援を提供することが可能です。
現在のケアマネジャーの平均年齢は53.6歳となっており、65歳以上の割合は13.6%を占めています。これらの数字からも分かるように、高齢者の活躍が当たり前の職種となっており、60代からの挑戦も決して珍しいことではありません。定年を設けていない事業所も多く、体力が続く限り何歳まででも働き続けられる環境が整っています。
受験資格の対象となる国家資格の詳細
ケアマネジャー試験の受験資格を得るために対象となる国家資格は多岐にわたります。医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士などが該当します。
これらの資格を既に保有している60代の方であれば、実務経験を積むことでケアマネジャー試験の受験資格を得ることができます。特に看護師や介護福祉士の資格を持つ方は、介護現場での実務経験を積みやすく、ケアマネジャーへのキャリアパスが比較的明確です。病院や介護施設での勤務経験がある方は、その経験を活かして新たな分野でのキャリア形成が可能です。
医療系の資格を持つ60代の方の場合、これまでの医療知識と経験を介護分野で活用することで、医療と介護の連携において重要な役割を果たすことができます。また、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持つ方は、相談援助の専門性を活かしたケアマネジメントを提供することが期待されます。
一方で、これらの資格を持たない60代の方でも、まず介護福祉士などの資格取得から始めることで、ケアマネジャーへの道筋を作ることが可能です。介護福祉士の受験資格には、介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)を修了し、3年以上の実務経験が必要ですが、60代から始める場合でも計画的に取り組めば十分に実現可能です。
実務経験の詳細な計算方法と注意点
実務経験を計算する際には、いくつかの重要なポイントがあります。まず、対象となる資格を保有していても、その資格に基づく直接的な援助業務が本来の業務として位置づけられていることが必要です。つまり、資格を持っているだけでは不十分で、実際にその資格を活用した業務に従事している必要があります。
実務経験期間は連続している必要はなく、複数の事業所での経験を合計することができます。また、異なる資格に基づく実務経験も通算することが可能です。例えば、介護福祉士として3年間、社会福祉士として2年間勤務した場合、合計5年間の実務経験として認められます。これは60代の方にとって非常に有利な制度です。
従事日数の計算については、実際に勤務した日数をカウントします。有給休暇や研修日なども勤務日として計算されますが、病気休暇や育児休業などの期間は含まれません。900日という基準は、5年間で平均的に週4日程度勤務することを想定した日数となっています。
実務経験証明書は、勤務先の事業所から発行してもらう必要があり、実務経験の詳細な内容や期間を記載したものでなければなりません。複数の事業所で勤務経験がある場合は、それぞれの事業所から証明書を取得する必要があります。60代の方の場合、過去の勤務先が閉鎖している可能性もあるため、早めに証明書の準備を進めることをお勧めします。
実務経験の対象となる業務内容の具体例
ケアマネジャー試験の受験資格となる実務経験は、単に介護現場にいるだけでは認められません。対象となる業務は、利用者に対する直接的な援助業務でなければなりません。具体的には、身体介護、生活援助、相談援助、機能訓練指導などが該当します。
身体介護には、入浴介助、排泄介助、食事介助、移動・移乗介助、体位変換、清拭、更衣介助などが含まれます。生活援助では、調理、洗濯、掃除、買い物代行、薬の受け取りなどの日常生活支援が対象となります。相談援助業務では、利用者や家族からの相談対応、ケアプランの説明、サービス調整などが実務経験として認定されます。
事務作業や清掃業務、調理業務のみに従事している場合は、実務経験として認められない場合があります。実務経験証明書には、具体的な業務内容を記載する必要があるため、勤務先の上司や人事担当者と事前に相談しておくことが重要です。
60代の方が実務経験を積む場合、体力的な制約を考慮した業務配置をお願いすることも可能です。重労働を避けながらも、利用者との関わりを持てる業務を中心に経験を積むことで、効果的にケアマネジャーへの道筋を作ることができます。また、これまでの職業経験を活かした相談援助業務に重点を置くことも有効な戦略です。
2025年度試験概要と申込み手続きの詳細
2025年度のケアマネジャー試験は、2025年10月12日(日)に実施される予定です。受験申込期間は地域によって異なりますが、東京都の場合は2025年6月2日(月)から6月30日(月)までとなっています。他の都道府県でも同様の時期に申込み期間が設定される予定のため、早めに自分の居住地域の詳細な日程を確認することが重要です。
試験の申込みには、実務経験証明書または実務経験(見込)証明書の提出が必須となります。実務経験(見込)証明書は、試験日までに実務経験要件を満たす見込みがある場合に使用できますが、実際に要件を満たさなかった場合は受験資格が失効するため注意が必要です。
申込み手続きには以下の書類が必要です。受験申込書、実務経験証明書または実務経験(見込)証明書、受験手数料、写真、資格証明書の写しなどです。受験手数料は都道府県によって異なりますが、一般的に8,000円から12,000円程度となっています。
60代の方が申込み手続きを行う際は、書類の準備に時間がかかる場合があるため、申込み期間開始の1ヶ月前には準備を始めることをお勧めします。特に実務経験証明書は、勤務先の事業所の協力が必要なため、早めに依頼することが重要です。
今後の制度改正の可能性と影響
2024年11月7日に開催された有識者による検討会において、現在の受験資格である「実務経験年数5年」に関して、年数短縮を検討する考えを厚生労働省が示しました。これは、ケアマネジャーの人材不足が深刻化していることを受けた措置で、今後受験資格が緩和される可能性があります。
検討されている変更内容には、実務経験年数の5年から3年への短縮や、対象職種の拡大などが含まれています。もし実務経験年数が短縮された場合、60代の方にとってはより早期にケアマネジャーになることができるメリットがあります。現在実務経験を積んでいる途中の方にとっては、大幅な時間短縮となる可能性があります。
ただし、制度改正の具体的な内容や実施時期はまだ決定されていないため、最新の情報を常にチェックしておくことが重要です。2025年時点では大きな制度改正は実施されない見込みですが、2027年の受験要件緩和に向けた動きが始まっています。
制度が緩和されることで競争が激化する可能性もあるため、60代の方にとっては現在の制度のうちに確実に合格しておくことも一つの戦略となります。また、制度改正により新たに受験資格を得る方が増えることで、より多様なバックグラウンドを持つケアマネジャーが誕生することが期待されています。
60代ケアマネジャーの活躍の場と具体的な職場環境
60代のケアマネジャーが活躍できる場は非常に多岐にわたります。居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所などが主な職場となります。それぞれの職場で求められる役割や業務内容が異なるため、自分の希望や体力に合わせて選択することが可能です。
特に居宅介護支援事業所では、利用者の自宅を訪問してケアプランを作成する業務が中心となるため、60代の方の豊富な人生経験や相談援助スキルが活かされます。利用者やその家族との関係構築においても、同世代または年上の方からの助言は信頼感を得やすい傾向があります。また、在宅での業務が多いため、体力的な負担が比較的少ないことも60代の方にとってメリットとなります。
地域包括支援センターでは、地域の高齢者に対する総合的な支援を行います。60代のケアマネジャーは、地域の資源や人脈を豊富に持っていることが多く、地域包括ケアシステムの要として活躍することが期待されています。また、地域住民との関係構築においても、同世代ならではの共感や理解が重要な役割を果たします。
施設系の職場では、入所者に対する継続的なケアマネジメントを提供します。60代のケアマネジャーは、入所者の多くが同世代であることから、利用者の気持ちや家族の心境をより深く理解することができます。また、若いスタッフに対する指導や教育においても、人生経験に基づいたアドバイスを提供することができます。
試験対策と効果的な学習方法
ケアマネジャー試験は、介護支援分野、保健医療サービス分野、福祉サービス分野の3分野から出題されます。60代の方が効率的に学習を進めるためには、自分の職歴や経験を活かせる分野から重点的に学習を始めることをお勧めします。これにより、既存の知識を活用しながら新しい知識を効率的に身につけることができます。
例えば、看護師出身の方であれば保健医療サービス分野、社会福祉士出身の方であれば福祉サービス分野から学習を始めると理解が深まりやすいでしょう。また、介護現場での実務経験がある方は、介護支援分野の学習において実際の業務経験と関連付けながら理解を深めることができます。
合格者の多くが300~500時間程度の学習を目安に計画しています。60代の方は時間に余裕があることが多いため、じっくりと腰を据えて学習に取り組むことができるのが大きなメリットです。毎日2~3時間の学習を継続することで、約6ヶ月程度で十分な準備が可能です。
過去問題の活用が最も重要です。ケアマネ試験は過去問題を徹底的に分析することで、出題傾向や重要ポイントを把握することができます。参考書やテキストを使用した基礎学習、模擬試験の受験、通信講座やスクール講義の利用も有効な学習方法です。60代の方の場合、オンライン講座を活用することで、自宅で快適に学習を進めることができます。
合格率と難易度の現状分析
ケアマネジャー試験の合格率は例年15~20%台で推移しており、令和に入ってからは20%前後となっています。第27回(2024年度)の合格率は32.1%と前年と比較して11%も高い合格率となりましたが、依然として難易度の高い資格といえます。この合格率の変動は、問題の難易度や受験者の質によって影響を受けます。
この合格率の低さは、試験の難易度が高いことを示していますが、逆に考えると合格すれば高い専門性を持つ証明となります。60代の方にとっては、これまでの人生経験や職業経験を活かして、しっかりとした対策を行えば十分に合格可能な試験です。特に、実務経験が豊富な方は、理論と実践を結びつけて理解することができるため、有利に試験に臨むことができます。
試験は全60問のマークシート方式(五肢択一)で、試験時間は120分となっています。出題分野は介護支援分野(25問)と保健医療・福祉分野(35問)に分かれており、各分野で概ね60%以上の正答が合格基準となります。この基準をクリアするためには、苦手分野を作らないバランスの取れた学習が重要です。
60代の受験者の中には、現役時代よりも集中して学習に取り組める方も多く、合格率が全体平均を上回るケースも見られます。時間的な余裕を活かして、じっくりと基礎から学習を積み重ねることで、確実に合格レベルに到達することが可能です。
独学による効果的な学習アプローチ
ケアマネ試験は、計画的に勉強すれば独学でも合格を目指すことができます。60代の方の場合、時間に余裕があることが多いため、じっくりと腰を据えて学習に取り組むことができるのが大きなメリットです。独学の最大の利点は、自分のペースで学習を進められることと、費用を抑えられることです。
独学のコツとしては、まず全体の学習計画を立て、1日あたりの学習時間を決めて継続することが重要です。60代の方にお勧めの学習スケジュールは、試験の6ヶ月前から本格的な学習を開始し、最初の2ヶ月で基礎知識の習得、次の2ヶ月で過去問題の演習、最後の2ヶ月で弱点分野の強化と模擬試験の受験を行うパターンです。
定期的に模擬試験を受けて自分の実力を確認し、弱点分野を重点的に学習することで効率的に合格レベルに到達することができます。模擬試験は書店で購入できる問題集を活用したり、オンラインの模擬試験サービスを利用したりすることで、本番に近い環境で実力を測ることができます。
60代の方が独学で学習を進める際は、体調管理も重要な要素となります。無理のない学習計画を立て、適度な休息を取りながら継続することが成功の鍵となります。また、同じ目標を持つ仲間との情報交換やモチベーション維持のために、地域の勉強会に参加することも効果的です。
2025年度試験に向けた具体的なスケジューリング
60代の方が2025年の試験に向けて学習を進める場合、2025年4月頃から本格的な学習を開始することが理想的です。この時期から始めることで、10月の試験まで十分な準備期間を確保することができます。春から夏にかけての時期は、基礎学習に集中し、涼しくなる秋には最終的な仕上げを行うという季節を考慮したスケジュールも効果的です。
4月から5月にかけては、基礎知識の習得期間として、参考書やテキストを使用した学習を中心に行います。この期間では、3つの分野の全体像を把握し、基本的な法律や制度について理解を深めます。6月から7月は、過去問題演習期間として、実際の試験問題を解きながら出題傾向を把握し、知識の定着を図ります。
8月から9月は、弱点分野の強化期間として、模擬試験の結果をもとに苦手分野を重点的に学習します。この時期には、知識の整理と記憶の定着を図るために、まとめノートの作成や暗記カードの活用も効果的です。10月の試験直前期間は、最終確認期間として、重要ポイントの復習と体調管理に重点を置きます。
学習時間の配分については、平日は2~3時間、休日は4~5時間程度を目安とすることをお勧めします。60代の方の場合、体力的な制約も考慮して、無理のない範囲で継続することが重要です。また、学習の質を高めるために、集中できる時間帯を見つけて効率的に学習を進めることも大切です。
実務研修の詳細内容と受講準備
ケアマネジャー試験に合格した後は、介護支援専門員実務研修の受講が必要です。この研修は「介護支援専門員として必要な知識、技能を有する介護支援専門員の養成を図ること」を目的としており、ケアマネジャーとして実際に業務を行うために欠かせない重要なステップです。
2025年の実務研修は、15日間の講習+3日間の実務(計87時間以上の研修)で構成されています。以前は44時間だった実務研修が87時間に大幅に増加しており、より充実した内容となっています。この研修は全日程出席が修了要件となっているため、60代の方は体調管理に十分注意して臨む必要があります。
研修では、ケアプランの作成など、介護支援専門員として業務を行う上で基礎となる知識及び技能について学びます。後期課程では実習で得られた気づきや課題を振り返り、グループワークを中心とした演習を通して介護支援専門員として備えるべき知識や技術、倫理観の拡大を図ります。
60代の方にとって、これまでの人生経験を活かしてグループワークに参加できることは大きなメリットです。若い受講者との意見交換を通じて、多角的な視点でケアマネジメントについて学ぶことができるでしょう。また、実習においても、利用者との関係構築において豊富な人生経験が活かされることが期待されます。
オンライン研修の活用と準備
2025年現在、多くの都道府県で介護支援専門員研修をオンライン方式で実施しています。東京都では、実務研修、更新・再研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修、専門研修などをWeb形式・参集形式により実施しています。このオンライン研修の導入により、60代の方にとって大きなメリットが生まれています。
オンライン研修の最大の利点は、自宅から受講できることです。通勤時間を節約でき、慣れた環境で学習に集中することができます。特に60代の方にとっては、移動の負担が軽減されることで、体力的な負担を抑えながら研修に参加することができます。また、自宅での受講により、必要に応じて休憩を取ったり、体調に合わせて受講環境を調整したりすることも可能です。
ただし、パソコンやインターネット環境の整備が必要なため、事前に準備を整えておくことが重要です。オンライン研修を受講するためには、安定したインターネット接続、ウェブカメラ、マイク機能付きのパソコンまたはタブレットが必要となります。技術的な不安がある場合は、事前に操作方法を練習しておくことをお勧めします。
オンライン研修では、グループワークや意見交換もオンライン上で行われます。60代の方にとって、デジタル技術の活用は新たな学習体験となりますが、これも現代のケアマネジメントに必要なスキルの一つとして捉えることができます。研修を通じて、デジタル技術を活用したコミュニケーション能力も身につけることができるでしょう。
資格登録手続きと継続的な学習体制
実務研修をすべて修了した方へ研修修了の証明書が交付され、それを各都道府県に提出、登録することで介護支援専門員証がようやく交付される流れになっています。介護支援専門員実務研修を修了したら、3か月以内に各都道府県の「介護支援専門員資格登録簿」へ登録申請を行わなければなりません。
この登録申請を怠ると、研修を修了してもケアマネジャーとして働くことができないため、60代の方は特に手続きを忘れないよう注意が必要です。登録手数料は都道府県によって異なりますが、一般的に5,000円から8,000円程度となっています。必要書類についても事前に確認し、早めに準備を進めることをお勧めします。
介護支援専門員は5年ごとに更新研修を受講する必要があり、また、専門研修や主任介護支援専門員研修など、さらなるスキルアップのための研修機会も豊富に用意されています。60代のケアマネジャーにとって、これらの継続研修は知識の更新だけでなく、他のケアマネジャーとの交流を深める貴重な機会でもあります。
継続的な学習とスキルアップが求められるケアマネジャーの仕事は、60代の方にとって知的好奇心を満たす楽しみでもあります。主任ケアマネジャーの資格取得や、認知症ケア専門士などの関連資格の取得によって、さらなるキャリアアップも可能です。これらの研修や資格取得を通じて、専門性を高めながら長期的なキャリア形成を図ることができます。
60代ケアマネジャーの就職・転職市場の現状
60代でのケアマネジャー転職は十分に現実的です。2025年現在、60代歓迎のケアマネジャー求人は39,124件と豊富にあり、多くの事業所で60代の方の経験と知識を求めています。このような求人数の多さは、高齢化社会の進展とともにケアマネジャーの需要が高まっていることを示しています。
特に注目すべきは、定年を設けていない事業所が多いことです。体力が続く限り何歳まででも働き続けられる環境が整っており、60代から新たにケアマネジャーとしてキャリアをスタートすることも珍しくありません。65歳以上の再雇用求人も存在し、年収358万円~346万円程度で募集されているケースもあります。
求人の特徴として、60代の方の人生経験と安定性を高く評価している事業所が多いことが挙げられます。利用者の多くが高齢者であることから、同世代の理解力や共感力を求める声が多く聞かれます。また、若いスタッフの指導や教育においても、60代の方の経験が重要な役割を果たすことが期待されています。
転職活動を成功させるためには、これまでの職歴や経験をどのように介護分野で活かせるかを明確に整理することが重要です。営業経験があれば利用者や家族との関係構築に、教育経験があればスタッフの指導に活かすことができます。面接では、なぜケアマネジャーを目指すのか、どのような貢献ができるのかを具体的に伝えることで、採用の可能性を高めることができます。
年収と給与体系の詳細分析
2025年のケアマネジャーの平均年収は429万円となっており、令和4年度のデータでは月給37万6,240円で年収換算すると約450万円となっています。60代の方でも、経験や勤務形態によってこの水準またはそれ以上の収入を得ることが可能です。
年齢別の年収データを見ると、45~49歳で年収469.8万円が最も高く、50~54歳で458万円となっています。60代のケアマネジャーも、これまでの経験や専門性によって同程度の収入を期待することができます。特に、医療系の資格を持つ方や管理職経験のある方は、より高い収入を得られる可能性があります。
働き方の選択肢も豊富で、常勤としてフルタイムで働く場合はもちろん、非常勤やパートタイムとして時間を調整して働くことも可能です。特に60代の方にとっては、体調や生活スタイルに合わせた柔軟な働き方ができることは大きなメリットです。週3日勤務や時短勤務なども選択できるため、プライベートとのバランスを取りながら働くことができます。
年収アップを図る方法としては、施設ケアマネになって夜勤に入ることで、夜勤手当による収入増加が期待できます。また、経験年数を重ねることで基本給の昇給も見込めます。管理職やリーダー職に就くことも収入向上の有効な手段であり、60代の方の豊富な人生経験や職業経験は、チームをまとめる管理職として高く評価されることが多くあります。
地域包括ケアシステムでの重要な役割
今後の介護制度において、地域包括ケアシステムの構築がますます重要になっています。60代のケアマネジャーは、地域の資源や人脈を豊富に持っていることが多く、地域包括ケアシステムの要として活躍することが期待されています。長年地域に住んでいる方であれば、地域の特性や資源について深い理解を持っており、それらを活用したケアマネジメントを提供することができます。
地域の医療機関、介護事業所、行政機関、民間団体などとのネットワーク構築において、60代の方の人生経験や社会経験は大きな強みとなります。これまでの職業生活で培った人脈や信頼関係を活かして、利用者にとって最適なサービス調整を行うことができます。また、地域の高齢者やその家族との関係構築においても、同世代ならではの共感や理解が重要な役割を果たします。
地域包括支援センターで働く60代のケアマネジャーは、地域住民との橋渡し役として重要な機能を担います。地域の高齢者が抱える様々な問題に対して、豊富な人生経験をもとにした助言やサポートを提供することで、地域全体の福祉向上に貢献することができます。
2025年には団塊の世代が75歳以上になり、要介護者の発生率増加に伴い、ケアマネジャーの需要が高まることが予想されています。この社会的背景からも、60代ケアマネジャーの活躍の場はさらに拡大していくことが見込まれ、地域包括ケアシステムにおける役割も一層重要になっていくでしょう。
長期的なキャリアビジョンと将来設計
60代からケアマネジャーとしてキャリアをスタートした場合、70歳まで働くことを考えると約10年間の活動期間があります。この期間を有効活用するためには、長期的なキャリアビジョンを持つことが重要です。最初の数年は実務経験を積み、基本的なケアマネジメントスキルを身につけることに集中し、その後段階的に専門性を高めていくという計画的なアプローチが効果的です。
最初の2~3年間は、実務経験の蓄積期間として、様々な事例に関わりながら基本的なケアマネジメントスキルを身につけます。この期間では、利用者との関係構築、アセスメント技術、ケアプラン作成、サービス調整などの基本業務を確実に習得することが重要です。
その後の期間では、専門分野の特化や後進の指導にあたることで、より価値の高いケアマネジャーとして成長することができます。認知症ケア、医療連携、地域づくりなど、特定の分野で専門性を高めることで、事業所内でのポジション向上や収入アップにもつながります。
また、主任ケアマネジャーの資格取得や、認知症ケア専門士などの関連資格の取得によって、さらなるスキルアップとキャリアアップを図ることも可能です。60代という年齢を活かし、長期的な視点で利用者と向き合うケアマネジャーとして、業界に貢献することが期待されています。独立して居宅介護支援事業所を開業するという選択肢もあり、これまでの経験を活かして自分らしい働き方を実現することも可能です。









コメント